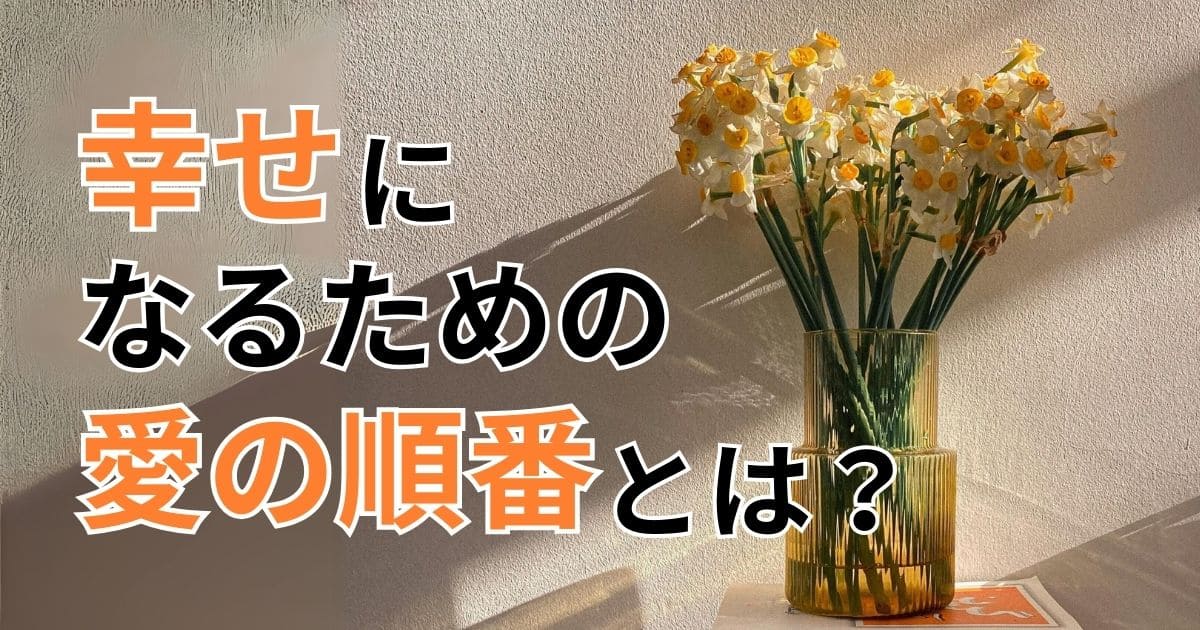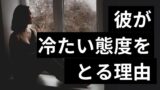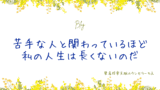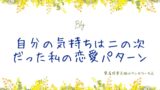人生何もうまくいかない…と悩む不安型愛着障害の方へ。
その原因は、「愛を受け取る」経験を十分に得られないまま「愛を与える」役割を強いられたことにあります。
本来あるべき「愛の順番」を取り戻すことが、不安型愛着障害の方が幸せな人生を築く鍵となります。
不安型愛着障害と「愛の順番」の関係

不安型愛着障害を抱える人が「幸せになれない」と感じやすい理由には、幼少期に経験する愛情のバランスの偏りがあります。
本来人は、以下の順番で愛を学び、育んでいくものです。
- 幼少期に愛をもらう:親や周囲から無条件の愛を受け、愛の存在とその意味を知る。
- 自分に愛を使う:自己肯定感を養い、自分自身を大切にする術を身につける。
- 他者に愛を与える:自分が満たされた状態で、他者にも健全な愛情を向ける。
しかし、不安型愛着障害を抱える人は、幼少期に十分な愛をもらう機会がなく、逆に「愛を与える」ことを求められる環境で育つことが多いのです。
親の機嫌を取る、親の期待に応えるといった「愛の役割を担わされる」経験を通して、本来あるべき愛の順番が逆転してしまいます。
この結果、大人になってからも愛の受け取り方や使い方が分からず、対人関係で苦労することが多いのです。
不安型愛着障害が抱える愛の問題

幼いころから愛を与えることを求められていた不安型愛着障害の人は、愛についての問題を抱えています。ここでは大きく分けて4つの問題を解説します。
1. 愛を受け取れない
幼少期に十分な愛を受けた経験が乏しいため、他者から愛情を受け取ること自体に抵抗を感じます。「愛される価値がない」と無意識に思い込み、褒められたり感謝されたりしても、それを素直に受け入れられないことがあります。
2. 愛を認識できない
愛情を受け取る機会が比較的少なかったことから、愛情表現に対する感度が鈍く、相手からの好意や配慮を「自分には関係ない」と解釈してしまいがちです。そのため、自分が愛されていることに気づかないまま、孤独感を抱え続けるケースも少なくありません。
恋愛において、不安や孤独感を感じるケースは愛を認識できないことが大きく関係しています。
関連記事↓
3. 愛を与えすぎる
愛を「与える」ことで価値を証明しようとする傾向が強いため、過剰に他者に尽くしてしまいます。結果として、精神的・体力的に疲れ果てるだけでなく、相手との関係性が一方的なものになりやすく、摩擦や衝突を生むこともあります。
「これだけ尽くしたのに相手は同じくらい返してくれない…だから私のことを愛してくれていないのだ」というような思考になりやすく、感情コントロールが利かなくなり感情を爆発させてしまいます。
↓関連ブログ
4. 愛の伝え方が分からない
愛情表現が不器用であったり過剰であったりするため、相手に「重い」と感じられて距離を置かれることもあります。これが「自分は愛されない」という誤った信念をさらに強化してしまう悪循環に陥ってしまうのです。
幸せになるための「愛の順番」を取り戻す

不安型愛着障害を克服し、幸せを手に入れるには、正しい「愛の順番」を取り戻すことが重要です。そのステップは次の通りです。
1. 愛をもらう:安全基地を作る
まず必要なのは、自分が安心して愛を受け取れる環境を整えることです。「安全基地」となる存在を見つけましょう。これは信頼できる家族や友人、恋人、あるいは専門のカウンセラーやセラピストが該当します。この安全基地の役割は、無条件にあなたを受け入れ、愛を提供してくれる存在であることです。
例えば
・「話を聞いてくれるだけでいい」と感じる相手に定期的に会う。
・自己開示の練習として、自分の思いや感情を言葉にして伝える。
ここで重要なのは、愛を「もらう」ことに罪悪感を感じないよう意識することです。「与えられるのが当然」と思えるようになるまで練習しましょう。
▼関連記事:恋人が冷たい気がする・・・と悩むあなたに。
2. 自分に愛を使う:自己愛を育む
愛を受け取る経験を積んだら、その愛を自分自身に使う方法を学びます。これには以下のアプローチが有効です。
自己肯定感を育む
・毎日、ポジティブな自己評価を言葉にする(例:「今日の私はよく頑張った」)。
・他人からの褒め言葉を否定せず、「ありがとう」と受け取る練習をする。
自己ケアを習慣化する
・体を休める時間を確保する(睡眠、運動、リラックスする時間)。
・自分が楽しめる趣味や活動を見つけ、それを優先する時間を作る。
自己の限界を知る
無理をして他者に尽くそうとする癖を見直し、「断ること」も愛の一つであると理解しましょう。
↓著者Instagram
3. 愛を与える:健全な人間関係を築く
自分を満たした後で、ようやく他者に愛を与える準備が整います。この段階では、愛情表現のバランスと適切な方法を意識することが大切です。
相手を尊重する愛の形
・相手の気持ちや状況を尊重する(押しつけではなく共感を意識)。
・自分の愛情が過剰でないか、冷静に振り返る習慣を持つ(日記を書くことが効果的)。
双方向の関係を築く
・自分ばかりが与えるのではなく、相手からも愛を受け取ることを忘れない。
・互いに成長し合える関係を目指す。
関連ブログ↓
克服のための実践的なアプローチ

不安型愛着障害を克服するには時間がかかりますが、少しずつ愛の順番を整えることで、確実に幸せへの道を歩むことができます。
愛着障害を自分だけで克服しようとするとかなり難易度が高まりますが、手軽に利用できるサポートツールを活用すれば克服への道が広がります。
そこでお勧めなのが、愛着障害克服経験を持った心理カウンセラーが監修した動画講座です。
仕事や育児で忙しい方でもスキマ時間を利用して愛着障害の克服を目指すことができます。
動画講座を公開している専用サイトでは、
・テキストコンテンツ「愛着障害さんが生きづらさを解消する方法」
・愛着障害の質問コーナー
・愛着障害の克服計画 など
様々なコンテンツを公開しており、愛着障害への理解を深めながら自分や他人に愛を実践する方法を学ぶことができます。
▼詳しい内容は画像をクリックしてください▼

終わりに

不安型愛着障害の克服には「愛の順番」を取り戻すことが欠かせません。愛をもらうことで自己愛を育み、それが他者への健全な愛へとつながります。
まずは、自分自身を許し、小さな一歩を踏み出してみましょう。その過程で「自分も愛されるべき存在だ」と気づくことができる日が必ず訪れます。そのとき、不安型愛着障害がもたらしていた不幸の連鎖を断ち切り、心から幸せだと感じられる人生を築けるのです。
あなたの人生が愛に溢れますように。
関連ブログ↓