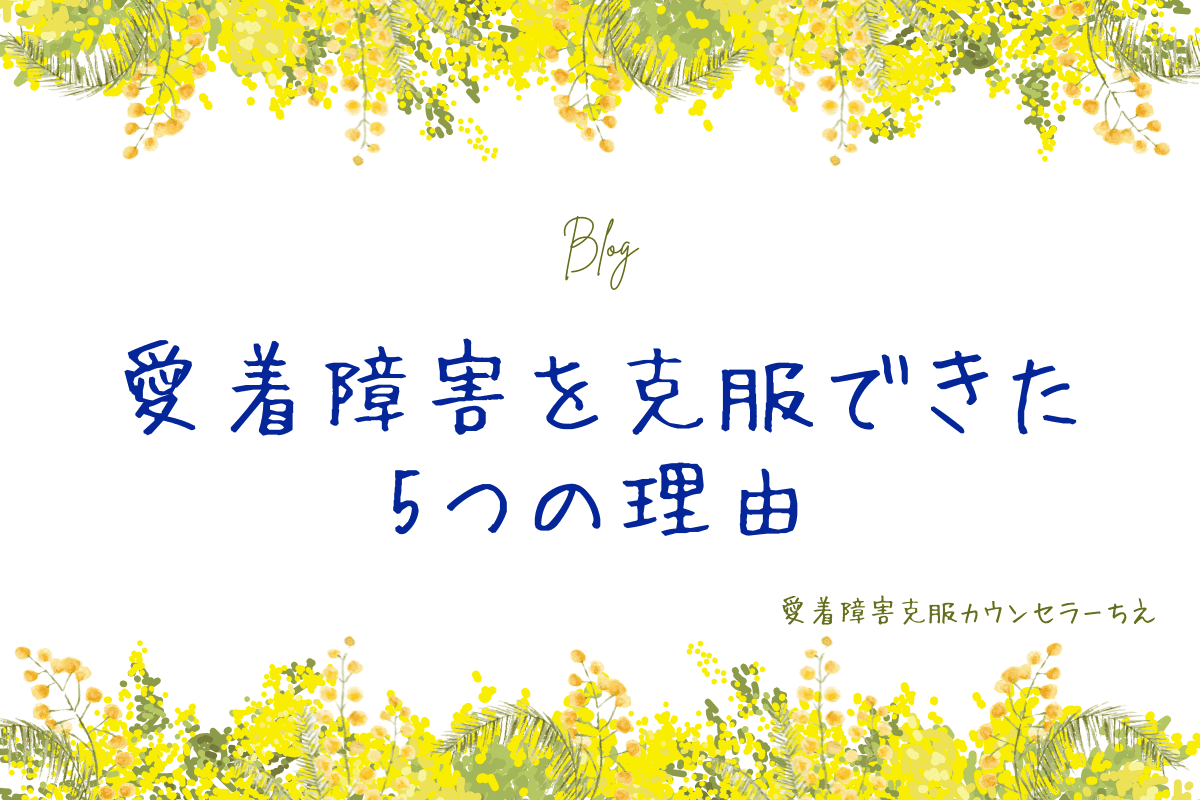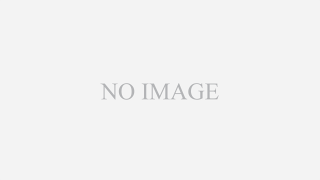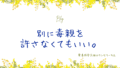かつての私は、人間関係がうまくいかない理由がわかりませんでした。
仲良くなればなるほど不安になり、相手の言動に一喜一憂し、心の中で相手を試すような行動をとってしまう自分がいました。
そんな自分に嫌気がさし、職場でもなじめず適応障害になっていた頃、「愛着障害」に出会ったのです。
愛着障害と闘った2年半の年月を振り返り、どうして私が愛着障害を克服できたのかを冷静に分析してみました。大きく分けて5つの理由を解説しましたので、ぜひご自分と比較してみてくださいね。
①不安型愛着の要素があったこと
私は愛着障害の中でも、不安型と回避型が複雑に混ざりあった「恐れ回避型愛着障害」でした。
相手に見捨てられることへの強い恐れ、自分には愛される価値がないのではという不安…。
そして、他人と仲良くなりたいのに突き放してしまいたい、どこか私のことを誰も知らないところに逃げてしまいたいと言った、回避型の傾向もありました。
愛着障害診断で、自分の愛着傾向が分かったときには、今までの行動パターンがまさにこれだ、と衝撃を受けました。
私の場合、幸いにも人を遠ざけようとする回避型の傾向よりも、不安型の傾向がやや高かったということもあり、回避型を不安型の要素が補完していました。
もしも回避型が他よりも群を抜いて傾向が高かった場合、愛着障害の克服はより難しいものだったと思います。
②自分だけでなく大切な人を傷つけていることを自覚した
私が愛着障害を克服しようと思ったきっかけは、どうして自分だけこんなにも生きづらいのだろうという疑問からでしたが、何よりも私が変わりたいと思ったきっかけは別にありました。
それは、自分が愛着障害を抱えていることで、大切な人たちを知らず知らずのうちに傷つけていたという事実です。
特に今もお付き合いしている彼の存在が大きいです。親の前では「いい子」でいられるのに、彼の前ではわがままで横暴な自分が出てきてしまい、自分では抑えきれない怒りの感情を止められなくなったのです。
何度も喧嘩をしましたし、そのたびに彼が悪いのだと責め続けました。しかし、愛着障害について知っていくにつれて、原因は私にあるのだと自覚しました。
私が変わる理由は、自分が幸せになることだけでなく、誰かを大切にするためでもあったのです。
③自分の残酷さが怖いと感じたこと
他人を見下す、突然冷酷な自分になる。こんな自分の中にある「残酷さ」をそれまでの私は見て見ぬふりをして生きてきました。でも、5年後、10年後の未来を想像した時に「このまま残酷な自分と一緒に生きていけるのか?」とふと考えてみると、本当に怖くなりました。
未来を変えたい、同じことを繰り返したくない、そんな強い思いが、変化への原動力になりました。
④独学での克服を挫折したこと
私は愛着障害を自覚してから1年ほど、独学で克服しようと本やネットで情報を集めました。
しかし、頭では理解していても、実際の感情や行動は簡単には変わりませんでした。
そんなとき、思い切ってプロのカウンセラーに相談しました。
専門家のサポートを受けることで、「愛着」は知識で学ぶものではなく、人との関係の中で少しずつ育まれるものだと実感しました。まるで一緒に愛着を育て直してもらっているような感覚でした。
⑤困ったら助けてくれる人がいるという安心感
家族や友人には話しにくいことも、カウンセラーや信頼できる第三者に話すことで、自分の中の「怖さ」が少しずつ和らいでいきました。「困ったときは助けてくれる人がいる」と思えることが、私にとっては大きな支えでした。
カウンセリングを始めるまでは、人に相談をするなんて弱い人のすることだと思っていた私の考えが変わりました。心から安心できる「助けて」と言える相手がいたことは愛着を再形成するにはなくてはならないことだったと感じています。
▼愛着障害克服に欠かせない「安全基地」の作り方
愛着障害に打ち勝つために
一人で悩む時間も私にはきっと必要だったのだと思いますが、人の支え無くして愛着障害の克服は難しかっただろうなと思います。
少なくとも今の私は、自分と他人の間に安心感のある関係を築けるようになりました。心の傷は、時間と人とのつながりの中で癒えていくのだと、身をもって感じています。
本当にどんな小さなことでも構いません。皆さんも一人で悩まず、誰かの力を借りて少しずつ前に進みませんか?
ぜひ、心理カウンセラーちえのサービスページもご覧ください。